愛国産のシンコウラブリイ、米国産のヒシマサルが1、2着を分けたのが92年のニュージーランドトロフィー。その年度に85頭だった輸入競走馬(血統登録馬)は、翌年189頭と倍増し、ピークとなった97年の453頭まで急激な伸びを見せる。1頭あたりの稼ぎが平均およそ1.4倍の外国産馬の頭数がそれだけ増えると、高まった圧力のはけ口が必要になるのは当然だろう。それまでのダービートライアルであったNHK杯を改称してニュージーランドTに置き換え、G1のラベルを貼り付けて出来上がったのがこのレース。成立の仕方はJRAの若いG1らしく、いかにも人工的だが、実際には当時の競走馬資源の変容をうけた極めて自然発生的な性格が強かった。
下に示したグラフは、棒が各年度のJRA在籍馬に占める輸入競走馬数(マル外+カク外)の割合で、折れ線がそれらがその年に稼いだ1頭あたりの総賞金。輸入数のピークは輸入後に実戦で稼働するまでの期間だけスライドして、量的には98年、質的には99年が頂点となっている。この時期のマル外といえば、タイキシャトルやエルコンドルパサーが代表的だが、タイキシャトルは98年いっぱいで引退、エルコンドルパサーも日本で戦ったのは98年までだから、ひと握りのエリートを除外してもなおアベレージが高い時代だった。2000年を過ぎると輸入競走馬の勢力減退は急激ではないが隠しようがない。04年度の輸入数は盛り返しているので、このまま下がり続けることもないだろうが、海外のセリで景気良く高額馬を落札するシーンは減り(昨年9月のキーンランドセールの9億円のストームキャット産駒などの例がたまにはあるけれど)、トレーニングセールのトップバイヤーに日本人の名前が挙がることもなくなった。今回登録のあるマル外も、海外での自家生産や預託生産、あるいはセリでの購買馬でもそれほど高くない価格のものばかりで、マル外ダービーの華やぎは完全に過去のものになった。
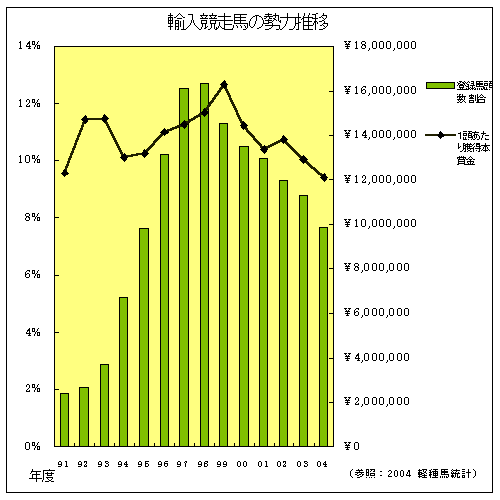
輸入競走馬の質×量が低下し、サンデーサイレンスもすでにない。日本の競馬は、このまま低迷の淵に沈んでしまうのだろうかと危惧する向きもあるかもしれないが、ことはそう一直線に進むものでもない。生産→競馬のサイクルは投資を回収するのに時間がかかる反面、血統という形でプールされているので、それが一夜にしてゼロになることはない。サンデーサイレンス系の資産とは別にマル外ブーム当時の貯金を元手に再上昇を果たす可能性は残されていて、昨年来のタイキシャトル産駒やマイネルラヴ産駒の活躍は、そのとっかかりともいえるだろう。インベーダーであったマル外が、強い味方に転じたのである。それが世紀の変わり目のマル外ブームの残したものだ。
エルコンドルパサーはこのレースが生んだ最強馬。00年から種牡馬入りして、02年の7月に急死し、産駒は現4歳から2歳まで3クロップを残した。自身の血統が完成された芸術品というべき性格が強かっただけに配合面での難しさがつきまとい、期待の大きさからするとこれまでの産駒の成績は物足りない。しかし、その能力を考えれば、壺に嵌まった配合なら大物が出る可能性はある。◎アイルラヴァゲインの配合がそれにあたるかどうかは分からないが、ひょっとするとそうかもしれないと思わせる要素は豊富に持っている。マル外のスプリンターだった母は、その父メドウレークの母の父として入るレイズアネイティヴ、そして他にもブルーラークスパーやマンノウォーといった重要な米国血脈を強く受けている。エルコンドルパサーを、ノーザンダンサーやハイペリオンによって欧州化の進んだミスタープロスペクター系と捉えるとすると、この母との配合は、欧州方面に行き詰まったところを米国血脈でニュートラルに引き戻し、新しい方向性を与えたと見ることもできる。特に祖母の父インリアリティはミスタープロスペクターにとって最強のサポート血脈で、アンブライドルドからスマーティジョーンズまで、ミスタープロスペクター系の米国クラシック勝ち馬の多くが母系からインリアリティの血を受けていた。スタミナを補強するとか、そういう算術的な血統論を超えて、この組み合わせでは、スピードとスピードがぶつかることで、クラシックで求められる特別な何かが得られるようだ。今のところそういう推測の域に止まらざるを得ないが、この配合にはミスタープロスペクター系特有の脆さを感じさせない例が多いのも確か。大レースを走ることで初めて引き出される部分を、この馬も秘めていそうに思う。10回目を迎える今年、父仔制覇が達成されれば、晴れてこのレースも一人前だ。
エルコンドルパサーの勝った年、マイネルラヴは0秒7差の7着だった。しかし、その年の暮れにはスプリンターズSでタイキシャトルを破っている。2歳で1800mをこなしたかと思うと、3歳の終わりには1200mで大金星を挙げ、強いのかと思うとその後は取りこぼしも多かった。基本的にスピード能力は高くても捉えどころのない面があって、しかし逆に種牡馬としてはその捉えどころのなさが懐の深さにつながってもいる。○マイネルハーティーは母の父も最強馬で天才で、しかし種牡馬としては捉えどころのなさが並大抵でないシンボリルドルフ。7年前の父の仇を今ここで!という場面があるかもしれない。
サンデーサイレンスは芝のG1ではこのレースと安田記念だけが未勝利。有力馬の出走機会が少ないのが最大の理由だろうが、サンデーサイレンス産駒がその爆発的な末脚を発揮するためのタメをつくる機会が少ないという流れの問題もあるかもしれない。▲ペールギュントは母がリファール×カロの桜花賞2着馬。一瞬の切れはトップクラスだが、東京だと、その最大の武器をどこで使うかがなかなか難しい。
名門牝系侮るべからずというのが天皇賞(春)の教訓。△パリブレストはケープクロス、シャダイード、アリダレスにラシアンリズムと現代欧州の名馬名牝が続々と出現する名門。この父もエルコンドルパサー相手なら目の色を変えるだろう。